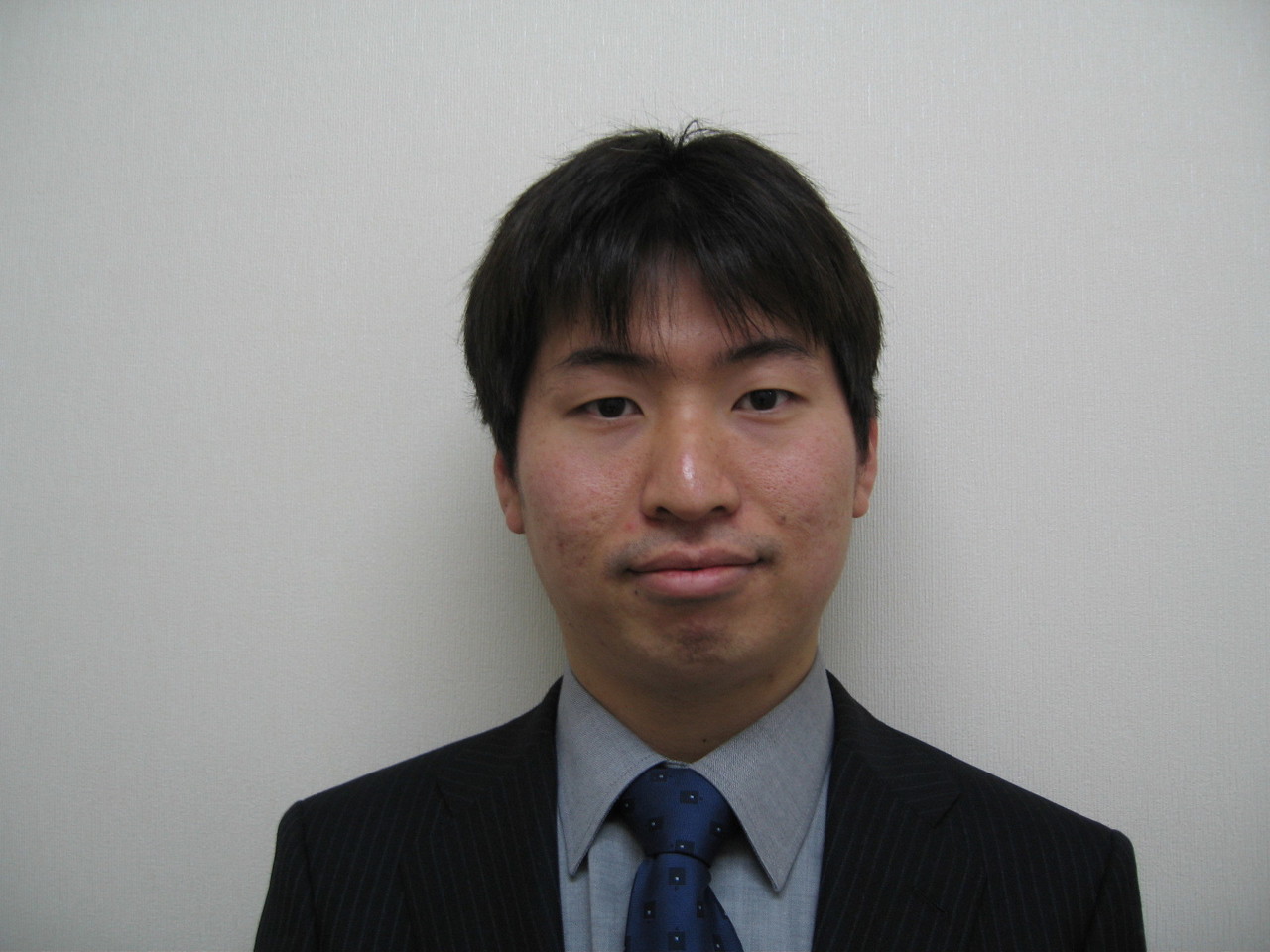〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
不動産購入・新築登記に関する注意点
不動産購入・新築における注意点を記載しています。ご覧になりたいページをご参照ください。
〇共有持分の決め方(2022/09/29作成)
〇連帯債務で借りるメリット(2024/11/25作成)
〇連帯債務で借りる際の持分の決め方~頭金なしの場合~(2024/11/26作成)
〇連帯債務で借りる際の持分の決め方~頭金ありの場合~(2024/11/26作成)
〇連帯保証型で保証人は持分を入れることが出来る?(2024/11/26作成)
共有持分の決め方
ご夫婦や親子等の複数人で共同して、住宅(不動産)を購入する場合、共有持分を
あらかじめ決めなければなりません。では共有持分はどのように決定すれば良いで
しょうか?この点、共有持分は、売買代金出資額に応じて決めるべきです。
何故なら、出資金額に応じないで決定すると、負担額との差額に対して贈与税が課
税されてしまうからです。
例えば、2000万円の住宅をAさんが1500万、Bさんが500万で購入したとしましょう。
この場合、出資金額で持分を決める場合Aさんは持分4分の3(1500÷(1500+500))
、Bさん持分4分の1(500÷(1500+500))となります。しかし、仮にAさん持分2分
の1、Bさん持分2分の1としてしまうと、Bさんの持分評価は1000万となり差額の500
万円をAさんから贈与を受けたものとみなされてしまいます。
よくある勘違いが、年収の割合で決めたり、夫婦共働きだからと安易に持分2分の1
と決められる方がおられますが、先ほども記載した通り、負担金額を無視すると贈与
税が課税されますのでお気を付けください。但し、婚姻期間が20年以上のご夫婦が
ご自宅を購入される場合は、一定の条件を満たせば2000万円の特別控除が受けられま
す。特別控除を受けることが出来る場合は、控除額の範囲内で出資金額を無視した持分
割合を決めることが出来ます。
連帯債務で借りる際のメリット
住宅ローンを借りる際、夫婦の一方を主債務者、もう一方を連帯債務者として借りるという方法
があります。この方法のメリットとしてはいくつかあります。
メリット①夫婦双方の収入を合算して借り入れできる
→連帯債務で借り入れる場合、夫婦双方の年収を合算して住宅ローンを組めます
ので、夫婦のいずれか一方の単独債務では希望額を借入できない時でも、連帯
債務だ希望額を借り入れできる可能性があります。
メリット②夫婦ともに住宅ローン減税の適用を受けることが出来る
→夫婦の二人ともが住宅ローン減税の条件を満たしていれば、適用を受けることが
可能となります。
メリット③諸費用が抑えられる
→連帯債務は一本の契約なので、事務手数料や印紙代等の諸費用がペアローンよりも
抑えることが出来ます。
連帯債務で借りる際の持分の決め方~頭金なしの場合~
住宅ローンを借りる際、連帯債務で借り入れする場合、主債務者だけではなく連帯債務者の持分
も入れることが出来ます。この際の持分の決め方にあたっては、夫婦の年収の割合によって決め
ることが合理的とされています。では具体的に見ていきましょう。
夫の年収 金400万円
妻の年収 金600万円
頭金 0円
購入代金 金3000万円
借入金額 金3000万円
この事例では、単純に年収で持分割合を決めますので、
夫:妻=400万:600万=2:3
となり、夫の持分5分の2、妻の持分5分の3とします。
連帯債務で借りる際の持分の決め方~頭金ありの場合~
住宅ローンを借りる際、連帯債務で借り入れする場合、主債務者だけではなく連帯債務者の持分
も入れることが出来ます。この際の持分の決め方にあたっては、夫婦の年収の割合によって決め
ることが合理的とされていますが、今回は頭金ありのケースで見ていきましょう。
夫の年収 金400万円
妻の年収 金600万円
頭金 金500万円(妻が支払う)
購入代金 金3000万円
借入金額 金2500万円
このケースにおいてはまず借入金額における夫または妻の負担割合を算出します。
夫→2500万円×400万/(600万+400万)=1000万
妻→2500万円×600万/(600万+400万)=1500万
妻は、頭金500万円を出していますので、上記の1500万円に加えます。そして、最終的な
割合は、夫:妻=1000万円:2000万=1:2となります。従って、持分割合は
夫→持分3分の1
妻→持分3分の2
となります。
連帯保証型で保証人は持分を入れることが出来る?
住宅ローンを借りる際、夫婦の一方が主債務者でもう一方が連帯保証人となるケースもありま
す。連帯債務は連帯債務者が主債務者と同等の債務を負うのに対して、連帯保証人は、主債務者
が返済できなくならない限り、債務を負うことはありません。
つまり、連帯保証人は住宅購入時の、住宅ローン借入時には何も出資していない事となります。
従って、連帯保証人について持分を入れることは出来ません。夫婦共有にしたいときは、連帯保証ではなく、連帯債務で借り入れることをお勧めします。
お問合せ・ご相談はこちら
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
| 対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
|---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
所有権更正・抹消
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
主な業務地域
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc